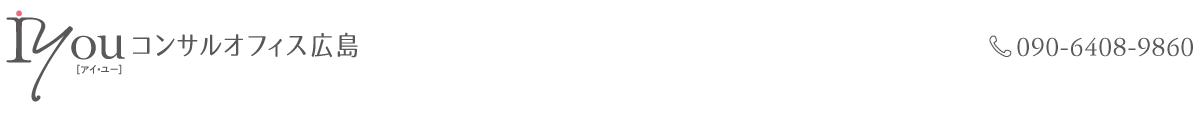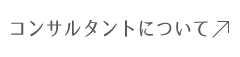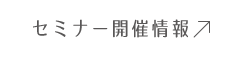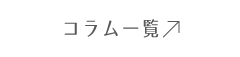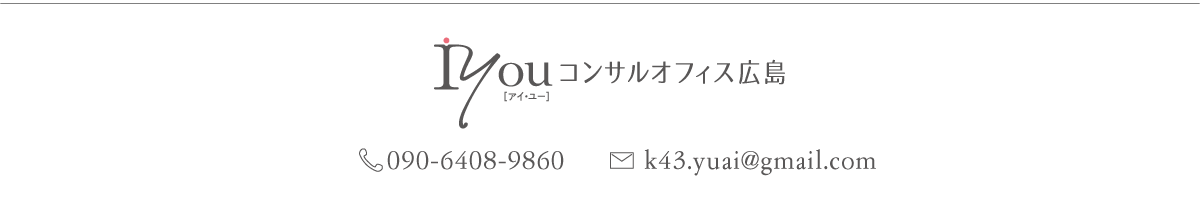皆様、こんにちは!
iyouコンサルオフィス広島の中岡です。
皆さんはお墓参りには行かれていますか?
私はまだ両親が生きていますので、これまでお墓参りは両親が行っているし…と、年に1回行くか行かないかでしたが、両親も高齢になり、今年から私が行くことが多くなりました。
お墓参りは3月と9月の彼岸、お盆、年末年始、命日や月命日などのタイミングで行く人が多いのではないでしょうか?
その時期にはお墓参りはしておかないと!という思いにはなりますが、そもそもお墓参りは何のためにするの?と、ふと気になり、調べてみました。
お墓参りは、自分のルーツであるご先祖様が眠る場所である「お墓」に出向き、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えるために行うもの…だそうです。
亡くなったご先祖に会える場所!がお墓だとすれば、亡くなる側より、生きている側がお墓を必要とし、お墓を守っていかなければならないのかもしれません。
いわゆる「墓守」です。
ですが、近年、少子化も進み、承継することが困難になり、お墓の在り方も変わってきたようです。
お墓以外に
1.永代供養墓での供養
2.納骨堂に安置
3.共同墓地に埋葬
4.自宅で供養
5.散骨、樹木葬
6.(ゼロ)葬
…と様々な選択があります。
故人の希望であればどの選択も多様であっていいとは思いますが、残された人はどうでしょう?
「墓守」をすることで、感謝の気持ちを伝えるはずだったお墓がないとなれば、その気持ちはどこに持っていけばいいのでしょうか?
例えば、散骨や樹木葬なら海や土に返します。
毎年、海や土に向かって気持ちを伝えるのでしょうか?
そして近年では亡くなった後、同じ場所(共同墓)に入る契約をし、その仲間で集うサークルがあるようです。
生きている間に仲良くしている友達同士で同じ場所に入るための墓友サークルで、友達同士で逝くことができると思うと、死という恐怖も和らぎ、楽しいかもしれないな…と、私も一瞬思いましたが、血縁がないとなると、お墓に入る前に揉めたりしないのかな?とか考えてしまいましたが、これも一つの選択肢ですね。
iyouコンサルオフィス広島の中岡です。
皆さんはお墓参りには行かれていますか?
私はまだ両親が生きていますので、これまでお墓参りは両親が行っているし…と、年に1回行くか行かないかでしたが、両親も高齢になり、今年から私が行くことが多くなりました。
お墓参りは3月と9月の彼岸、お盆、年末年始、命日や月命日などのタイミングで行く人が多いのではないでしょうか?
その時期にはお墓参りはしておかないと!という思いにはなりますが、そもそもお墓参りは何のためにするの?と、ふと気になり、調べてみました。
お墓参りは、自分のルーツであるご先祖様が眠る場所である「お墓」に出向き、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えるために行うもの…だそうです。
亡くなったご先祖に会える場所!がお墓だとすれば、亡くなる側より、生きている側がお墓を必要とし、お墓を守っていかなければならないのかもしれません。
いわゆる「墓守」です。
ですが、近年、少子化も進み、承継することが困難になり、お墓の在り方も変わってきたようです。
お墓以外に
1.永代供養墓での供養
2.納骨堂に安置
3.共同墓地に埋葬
4.自宅で供養
5.散骨、樹木葬
6.(ゼロ)葬
…と様々な選択があります。
故人の希望であればどの選択も多様であっていいとは思いますが、残された人はどうでしょう?
「墓守」をすることで、感謝の気持ちを伝えるはずだったお墓がないとなれば、その気持ちはどこに持っていけばいいのでしょうか?
例えば、散骨や樹木葬なら海や土に返します。
毎年、海や土に向かって気持ちを伝えるのでしょうか?
そして近年では亡くなった後、同じ場所(共同墓)に入る契約をし、その仲間で集うサークルがあるようです。
生きている間に仲良くしている友達同士で同じ場所に入るための墓友サークルで、友達同士で逝くことができると思うと、死という恐怖も和らぎ、楽しいかもしれないな…と、私も一瞬思いましたが、血縁がないとなると、お墓に入る前に揉めたりしないのかな?とか考えてしまいましたが、これも一つの選択肢ですね。
そして代々引き継がれてきた墓守の形も変わり、毎年お墓参りに行けない人に代わり「お墓参り代行サービス」というものを利用する人もいるようです。
これもお墓参りの目的を果たしているのかの疑問は残りますが、一つの選択肢には違いありません。
が、私がお墓の中にいたなら、全くの他人が目の前で手を合わせてくれたところで「あなた誰?」とツッコミそうですが(笑)
どちらにしろ、このように多様化しているお墓問題の背景には、すでに社会問題となっている少子高齢化があります。
「墓守」するも「墓じまい」するも、どちらも費用がかかります。
それにより、承継できなくなる家族が多くなれば、間違いなくこれからの社会の課題となっていくことでしょう。
どちらを選択するかは個人の自由です。
各家族でどうするべきかを生きているうちにしっかり話し合う必要があるかもしれませんね。
そして、お墓も所有する時代から共有(シェア)することが当たり前になっていくのかもしれません。
これも時代の変化というものでしょうか…
これもお墓参りの目的を果たしているのかの疑問は残りますが、一つの選択肢には違いありません。
が、私がお墓の中にいたなら、全くの他人が目の前で手を合わせてくれたところで「あなた誰?」とツッコミそうですが(笑)
どちらにしろ、このように多様化しているお墓問題の背景には、すでに社会問題となっている少子高齢化があります。
「墓守」するも「墓じまい」するも、どちらも費用がかかります。
それにより、承継できなくなる家族が多くなれば、間違いなくこれからの社会の課題となっていくことでしょう。
どちらを選択するかは個人の自由です。
各家族でどうするべきかを生きているうちにしっかり話し合う必要があるかもしれませんね。
そして、お墓も所有する時代から共有(シェア)することが当たり前になっていくのかもしれません。
これも時代の変化というものでしょうか…